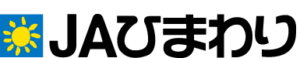農畜産物を生産・出荷している方をご紹介します


農畜産物を
生産・出荷している方を
ご紹介します
愛情を注いだ分だけ返ってくる。それが農業
いちご部会所属 近藤 透さん
苗づくりが鍵
現在は26アールのハウスで、部会品種の「とちおとめ」を栽培する透さんは農業を始めてからおよそ40年が経ちました。イチゴの栽培で大切なことは「育苗」と呼ばれる苗づくりです。育苗の段階で炭疽病などの病気が見つかると、多くの苗に影響してしまうため、早期に対応しないといけません。苗づくりはとても重要な作業なことから、「満足できる苗が出来たら半分は成功したようなもんだよ」と透さんは話します。今期の夏は暑い日が多く、水やりの頻度や与える量などに苦労したそうです。
環境モニタリング装置で
ストレスを与えない
透さんが積極的に導入しているのは環境モニタリング装置です。温度、炭酸ガス、給液などはハウス内の状況に応じて自動的に対応できます。また、スマートフォンでハウス内のデータを見ることや、遠隔操作も可能です。イチゴの株にストレスを与えず、適切な施肥量を図ることにより、肥料の削減や収量の確保、美味しさに繋げています。透さんは「自動でデータが蓄積されていくから今後イチゴの栽培を始める人の参考にもなる」と今後を見据えています。ただ、毎日1回は必ずハウスを見に行き、直で確認することも欠かさないそうです。 そんな透さんは「愛情をかけて育てたものが収穫できる時が最高の喜びで、それが農業だと思う。食べた人に美味しいと言ってもらえたらなおさらうれしい」と笑顔で話してくれました。

部会とともに
販売指導課 いちご部会担当
寺脇 康太さん
お互いの印象は?
近藤さん:会った当初から知識があり、いちごが好きな印象があります。
寺脇さん:知識が豊富な上に、勉強熱心な生産者という印象です。
あなたにとってどんな存在ですか?
近藤さん:頼りがいのある存在です。
寺脇さん:栽培で発生する病気のことや部会のことについて相談でき、頼りになる存在です。
相手の方にメッセージをどうぞ
近藤さん:優しい人ですが、イチゴに対しては強気な考えを言ってもらいたいと感じています。若い世代の生産者とタッグを組んで部会を盛り上げてほしい!
寺脇さん:いつも相談ごとや困りごとを聞いてくださってありがとうございます。これからも引き続きお願いします。

近藤さんが所属している
いちご部会
| 部会員数 | 96名 |
| 栽培面積 | 16ha |
| 販売数量 | 264万パック |
| 販売金額 | 9億円 |
透さんのハウスに導入されている環境制御装置「はかる蔵」の子機です。上部の小さな穴がセンサーに繋がっており、気温・湿度・地温・日照・二酸化炭素の測定が可能です。



果樹・野菜を
育てる難しさと
収穫の時の楽しみ
育てる難しさと
収穫の時の楽しみ
濵本 延夫さん 瀬木町

家の前にあるスペースを利用して家庭菜園を楽しんでいる延夫さんは、およそ10年前から旬の野菜を育てるようになりました。この冬もダイコン・ミズナ・レタス・コマツナなどの種を植え、それぞれ収穫の時期を迎えました。かつては三ケ日でミカンの収穫を手伝っていたこともあり、「家にもミカンを植えたい」と、青島・不知火・ハルカの3品種のカンキツを植えました。カンキツの剪定作業は上を伸ばさずに横に広げていくのが基本とされていますが、花芽の見分け方や、枝を切るバランスなどとても難しい作業だそうです。
野菜が植わっている土地はもともと駐車場として利用していたので、砂利が多く、土壌づくりが必要です。植えるものに合わせてスペースを作り、堆肥などを活用します。堆肥は地元の肥育農家のものを使っています。限られたスペースに野菜を植えるので、連作障害に気を使います。本を参考にして土壌を作っており、これまで障害は特になく栽培できているそうです。
そんな延夫さんは「家族で食べる分を育てているけど、たくさん収穫したときは若夫婦や近所の知人に分けると喜んでくれるのでうれしい。これからも無理なく続けていけたらいいな」と笑顔で話してくれました。

農畜産物を生産・出荷している方をご紹介します


農畜産物を
生産・出荷している方を
ご紹介します
愛情を注いだ分だけ返ってくる。それが農業
いちご部会所属 近藤 透さん
苗づくりが鍵
現在は26アールのハウスで、部会品種の「とちおとめ」を栽培する透さんは農業を始めてからおよそ40年が経ちました。イチゴの栽培で大切なことは「育苗」と呼ばれる苗づくりです。育苗の段階で炭疽病などの病気が見つかると、多くの苗に影響してしまうため、早期に対応しないといけません。苗づくりはとても重要な作業なことから、「満足できる苗が出来たら半分は成功したようなもんだよ」と透さんは話します。今期の夏は暑い日が多く、水やりの頻度や与える量などに苦労したそうです。
環境モニタリング装置で
ストレスを与えない
透さんが積極的に導入しているのは環境モニタリング装置です。温度、炭酸ガス、給液などはハウス内の状況に応じて自動的に対応できます。また、スマートフォンでハウス内のデータを見ることや、遠隔操作も可能です。イチゴの株にストレスを与えず、適切な施肥量を図ることにより、肥料の削減や収量の確保、美味しさに繋げています。透さんは「自動でデータが蓄積されていくから今後イチゴの栽培を始める人の参考にもなる」と今後を見据えています。ただ、毎日1回は必ずハウスを見に行き、直で確認することも欠かさないそうです。 そんな透さんは「愛情をかけて育てたものが収穫できる時が最高の喜びで、それが農業だと思う。食べた人に美味しいと言ってもらえたらなおさらうれしい」と笑顔で話してくれました。

部会とともに
販売指導課 いちご部会担当
寺脇 康太さん
お互いの印象は?
近藤さん:会った当初から知識があり、いちごが好きな印象があります。
寺脇さん:知識が豊富な上に、勉強熱心な生産者という印象です。
あなたにとってどんな存在ですか?
近藤さん:頼りがいのある存在です。
寺脇さん:栽培で発生する病気のことや部会のことについて相談でき、頼りになる存在です。
相手の方にメッセージをどうぞ
近藤さん:優しい人ですが、イチゴに対しては強気な考えを言ってもらいたいと感じています。若い世代の生産者とタッグを組んで部会を盛り上げてほしい!
寺脇さん:いつも相談ごとや困りごとを聞いてくださってありがとうございます。これからも引き続きお願いします。

近藤さんが所属している
いちご部会
| 部会員数 | 96名 |
| 栽培面積 | 16ha |
| 販売数量 | 264万パック |
| 販売金額 | 9億円 |
透さんのハウスに導入されている環境制御装置「はかる蔵」の子機です。上部の小さな穴がセンサーに繋がっており、気温・湿度・地温・日照・二酸化炭素の測定が可能です。



果樹・野菜を
育てる難しさと
収穫の時の楽しみ
育てる難しさと
収穫の時の楽しみ
濵本 延夫さん 瀬木町

家の前にあるスペースを利用して家庭菜園を楽しんでいる延夫さんは、およそ10年前から旬の野菜を育てるようになりました。この冬もダイコン・ミズナ・レタス・コマツナなどの種を植え、それぞれ収穫の時期を迎えました。かつては三ケ日でミカンの収穫を手伝っていたこともあり、「家にもミカンを植えたい」と、青島・不知火・ハルカの3品種のカンキツを植えました。カンキツの剪定作業は上を伸ばさずに横に広げていくのが基本とされていますが、花芽の見分け方や、枝を切るバランスなどとても難しい作業だそうです。
野菜が植わっている土地はもともと駐車場として利用していたので、砂利が多く、土壌づくりが必要です。植えるものに合わせてスペースを作り、堆肥などを活用します。堆肥は地元の肥育農家のものを使っています。限られたスペースに野菜を植えるので、連作障害に気を使います。本を参考にして土壌を作っており、これまで障害は特になく栽培できているそうです。
そんな延夫さんは「家族で食べる分を育てているけど、たくさん収穫したときは若夫婦や近所の知人に分けると喜んでくれるのでうれしい。これからも無理なく続けていけたらいいな」と笑顔で話してくれました。

農畜産物を生産・出荷している方をご紹介します


農畜産物を
生産・出荷している方を
ご紹介します
選ばれる牛にするために
肥育牛部会所属 稲垣 浩輝さん
繁殖・肥育という仕事
「幼少期から牛と過ごす生活が当たり前にあった」と話す浩輝さん。自宅前には牛舎があり、酪農を営んでいました。一度は会社勤めをしましたが、10年ほど前から専業の畜産農家となり、令和2年、地元の畜産農家と共同で「大木預託牧場」の経営を始めました。 肉牛農家には様々な経営形態がありますが、浩輝さんは「繁殖経営」と「肥育経営」を行っています。仔牛を出産させ、8~10カ月齢まで肥育し、出荷するまでが仕事です。母牛、仔牛など合わせて200頭ほどを常時管理しています。
選ばれる牛にするために
牛の体調管理は最も大切な仕事のひとつです。人間と同じように寒暖差が激しいと風邪を引きやすくなります。特に仔牛は免疫力が低く、すぐに体調を崩しがちです。体調が悪くなると餌を食べず、体重の低下につながります。競りでは見た目や体重なども判断材料となるので、体調の悪い牛は早期に発見し、対応しなければいけません。日頃から愛情をかけ「なつかせる」と人間に対するストレスがなくなり、体調管理もしやすくなるそうです。 浩輝さんには経営や畜産のノウハウを学ぶ教科書のような存在が共同経営者におり、自分に足りない部分などを日々学んでいます。 そんな浩輝さんは「日本でもトップクラスの技術を学び、選ばれる牛を育てたい」と話してくれました。

部会とともに
畜産課 肥育牛部会担当
鈴木 謙吾さん
お互いの印象は?
稲垣さん:新入職員ということでこれからよろしくお願いします。
鈴木さん:若い世代で畜産をされていて、牛の扱いなどを学ばせてもらっています。
あなたにとってどんな存在ですか?
稲垣さん:競り子(競売で自札を挙げる役)を担ってくれており、農家と一緒になって頑張ってくれる存在です。
鈴木さん:学校で学んだことよりも現場で学ぶことが多く、稲垣さんからも多くの学ぶ機会をいただいています。
相手の方にメッセージをどうぞ
稲垣さん:これからも頑張っていこうね。期待しています。
鈴木さん:期待に応えられるように頑張ります!

稲垣さんが所属している
肥育牛部会
| 部会員数 | 3名 |
| 飼育頭数 | 380頭 |
| 生産品目 | 肉牛 肉用子牛 |
| 生産時期 | 通年 |
牛には個体識別番号があり、すべての牛は家畜改良事業団に出生届が出され、インターネット上にて個体の生年月日・飼養所在地(生育場所)・飼養者(生産者)・移動記録・母牛の確認が出来るようになっています。



日々の手入れで〝創る〟
気持ちの良い庭
気持ちの良い庭
山口 光弘さん 正岡町

松の木を中心に、槇、椿、サツキ、台杉、ヤマボウシ、梅、柿、柘植などが配置されている光弘さんの庭は、庭師が提案する図面をもとに構成されています。大きな木の剪定は庭師が5年後、10年後を見据えて行います。根元の雑草取りや、庭の周りを囲むカイヅカイブキの剪定、年に5回ほどの消毒、芝の手入れは光弘さんの日課です。 もともと庭いじりが好きなわけではなく、庭があるから手入れしないといけないとの気持ちでやっていました。ただ、せっかくなら綺麗な庭を保ちたいと時間があれば雑草取りなどを行うようにしています。冬になると虫の習性を利用して幹に藁を巻き付けます。これは「こも巻き」といって藁を編んで作られる「こも」に虫をおびき寄せて木を守る方法です。「効果があるのかわからないけど、景観は悪くないかな」と話します。
また、芝は一番手入れが大変です。特に際を剪定ばさみでこまめに刈らないと根がすぐに伸びてきます。また、根切りを行わないと生育に悪影響が出ます。範囲も広いので、どちらも肉体的にきつい作業だそうです。 そんな光弘さんは「綺麗な庭は自分が気持ちいい。お客さんが来た時でも綺麗だねと言ってもらえたらうれしい」と笑顔で話してくれました。