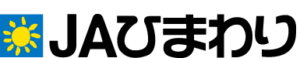農畜産物を生産・出荷している方をご紹介します


農畜産物を
生産・出荷している方を
ご紹介します
無限大の可能性があり、選択肢も広い。
農業は楽しいと思える仕事
農業は楽しいと思える仕事
鉢物部会所属 桑名 賢人さん
毎日花のことを考えないと
就農しておよそ10年の賢人さんは、約50アールの温室でシクラメンとポットカーネーションを栽培しています。父親が農業を頑張って続けている姿を見て、農業を継ぐことを決めました。農業は基本的に毎日花の様子を見て、管理します。ある年、花に病気の被害がたくさん出てしまったことで出荷量が減ってしまい、大きなショックを受けたことがありました。その時に、毎日花のことを考えて仕事をしないといいものが作れないと感じたそうです。シクラメンはおよそ3万5000鉢を出荷しますが、出荷されるまで1つ1つ状態を見て手入れしています。
シクラメンは出荷まで 1年ほど手をかける
賢人さんは12月から1月頃にシクラメンの種を植え、成長していくと植え替えをし、葉が鉢の周りを囲むように葉組作業をします。花がきれいに咲くためには肥料をあげるタイミングが重要です。肥料の種類や濃度も調整しないと咲くのが早すぎるなどの影響が出ててしまいます。特に夏場の管理は気を使います。肥料を抑えつつ、病害虫対策をし、花が傷まないようにしないといけません。出荷までおよそ1年、手をかけ続けています。今後は猛暑や虫の被害を抑えられるような新技術の導入も検討しています。
そんな賢人さんは「農業は無限大の可能性があって、選択肢も広く、自分で決められる。楽しいと思える仕事です」と話してくれました。

部会とともに
花き課 鉢物部会担当
野澤 祐也さん
お互いの印象は?
桑名さん:常に部会員のことをよく考えている印象です。知識も豊富です。
野澤さん:お願いごとも柔軟に対応してくれる優しい方です。
あなたにとってどんな存在ですか?
桑名さん:野澤さんや他の職員を通じて自分では確認できない他の生産者の情報や農業の情報を共有していただいているので助かっています。
野澤さん:とても頼りになる若手生産者です。
相手の方にメッセージをどうぞ
桑名さん:これからも鉢物部会が成長できるように尽力してほしいです!
野澤さん:これからも技術向上を目指した生産を続けていただきたいです!

桑名さんが所属している
鉢物部会
| 生産者数 | 26名 |
| 販売数量 | 46万鉢(シクラメン) |
| 販売金額 | 12.6億円 |
鉢物部会では主に11月下旬から12月下旬にかけてシクラメンを出荷しています。母の日向けのポットカーネーションは4月下旬から5月中旬に出荷します。また、部会では他の鉢物や観葉植物も生産しています。



いつでも新鮮な野菜を 食べられるのは
家庭菜園の醍醐味
西川 隆子さん
御油町

もともと庭に花を植えることが好きだった隆子さんは、ご主人の定年退職を機に家庭菜園を始めました。植木好きなご主人は庭の東側、西側の畑は隆子さんが使います。「分けておかないとケンカになるから」と笑顔で話します。それでも、収穫後に土を耕したり、堆肥を運んだり、ご主人にも協力してもらい家庭菜園を楽しんでいます。
今年も、ブロッコリー、ホウレンソウ、コマツナ、チマサンチュ、つぼみ菜など好きな冬野菜を植えました。畑だけではなくサラダ用に生で食べられる野菜をプランターで栽培します。野菜は種から育て、種を蒔く日をずらして長い期間収穫できるようにします。自分で食べる野菜なので、消毒はめったにしません。20年以上、自分なりに楽しんできました。 ただ、今年最初に種を蒔いたホウレンソウは、土の中で種がなくなってしまったそうです。それは今年の猛暑のせいでした。土の中で蒸されてしまい、腐ってしまったと考えられます。隆子さんは「今までにこんなことは無かった」と話します。また、暑い日が続いたせいで、虫の被害も多く、今までと比べても大変な年でした。今は、4回目に種を蒔いたホウレンソウがすくすくと伸びてきました。
隆子さんは、「お店で売っている野菜はきれいだけど、私は土の付いた野菜を家で採ってすぐに食べたい。これが一番新鮮でしょ」と笑顔を見せてくれました。

農畜産物を生産・出荷している方をご紹介します


農畜産物を
生産・出荷している方を
ご紹介します
無限大の可能性があり、選択肢も広い。
農業は楽しいと思える仕事
農業は楽しいと思える仕事
鉢物部会所属 桑名 賢人さん
毎日花のことを考えないと
就農しておよそ10年の賢人さんは、約50アールの温室でシクラメンとポットカーネーションを栽培しています。父親が農業を頑張って続けている姿を見て、農業を継ぐことを決めました。農業は基本的に毎日花の様子を見て、管理します。ある年、花に病気の被害がたくさん出てしまったことで出荷量が減ってしまい、大きなショックを受けたことがありました。その時に、毎日花のことを考えて仕事をしないといいものが作れないと感じたそうです。シクラメンはおよそ3万5000鉢を出荷しますが、出荷されるまで1つ1つ状態を見て手入れしています。
シクラメンは出荷まで 1年ほど手をかける
賢人さんは12月から1月頃にシクラメンの種を植え、成長していくと植え替えをし、葉が鉢の周りを囲むように葉組作業をします。花がきれいに咲くためには肥料をあげるタイミングが重要です。肥料の種類や濃度も調整しないと咲くのが早すぎるなどの影響が出ててしまいます。特に夏場の管理は気を使います。肥料を抑えつつ、病害虫対策をし、花が傷まないようにしないといけません。出荷までおよそ1年、手をかけ続けています。今後は猛暑や虫の被害を抑えられるような新技術の導入も検討しています。
そんな賢人さんは「農業は無限大の可能性があって、選択肢も広く、自分で決められる。楽しいと思える仕事です」と話してくれました。

部会とともに
花き課 鉢物部会担当
野澤 祐也さん
お互いの印象は?
桑名さん:常に部会員のことをよく考えている印象です。知識も豊富です。
野澤さん:お願いごとも柔軟に対応してくれる優しい方です。
あなたにとってどんな存在ですか?
桑名さん:野澤さんや他の職員を通じて自分では確認できない他の生産者の情報や農業の情報を共有していただいているので助かっています。
野澤さん:とても頼りになる若手生産者です。
相手の方にメッセージをどうぞ
桑名さん:これからも鉢物部会が成長できるように尽力してほしいです!
野澤さん:これからも技術向上を目指した生産を続けていただきたいです!

桑名さんが所属している
鉢物部会
| 生産者数 | 26名 |
| 販売数量 | 46万鉢(シクラメン) |
| 販売金額 | 12.6億円 |
鉢物部会では主に11月下旬から12月下旬にかけてシクラメンを出荷しています。母の日向けのポットカーネーションは4月下旬から5月中旬に出荷します。また、部会では他の鉢物や観葉植物も生産しています。



いつでも新鮮な野菜を 食べられるのは
家庭菜園の醍醐味
西川 隆子さん
御油町

もともと庭に花を植えることが好きだった隆子さんは、ご主人の定年退職を機に家庭菜園を始めました。植木好きなご主人は庭の東側、西側の畑は隆子さんが使います。「分けておかないとケンカになるから」と笑顔で話します。それでも、収穫後に土を耕したり、堆肥を運んだり、ご主人にも協力してもらい家庭菜園を楽しんでいます。
今年も、ブロッコリー、ホウレンソウ、コマツナ、チマサンチュ、つぼみ菜など好きな冬野菜を植えました。畑だけではなくサラダ用に生で食べられる野菜をプランターで栽培します。野菜は種から育て、種を蒔く日をずらして長い期間収穫できるようにします。自分で食べる野菜なので、消毒はめったにしません。20年以上、自分なりに楽しんできました。 ただ、今年最初に種を蒔いたホウレンソウは、土の中で種がなくなってしまったそうです。それは今年の猛暑のせいでした。土の中で蒸されてしまい、腐ってしまったと考えられます。隆子さんは「今までにこんなことは無かった」と話します。また、暑い日が続いたせいで、虫の被害も多く、今までと比べても大変な年でした。今は、4回目に種を蒔いたホウレンソウがすくすくと伸びてきました。
隆子さんは、「お店で売っている野菜はきれいだけど、私は土の付いた野菜を家で採ってすぐに食べたい。これが一番新鮮でしょ」と笑顔を見せてくれました。

農畜産物を生産・出荷している方をご紹介します


農畜産物を
生産・出荷している方を
ご紹介します
バラの花開く最後の瞬間まで
経過も楽しんでほしい
経過も楽しんでほしい
バラ部会所属 遠山 剛世さん
思い通りにいかないことを 実感させられる
6年程前に実家のバラ農家で農業を始めた剛世さん。約80アール、8棟の温室で約20品種のバラを栽培しています。剛世さんは新品種を3割ほど、定番品種を7割ほど栽培し、市場のニーズに合わせています。新品種は全て人気が出るわけではないので、早ければ1年で植え替えることもあるそうです。通常は株を定植すると3~4年の間、バラが収穫できます。剛世さんの目標は収穫量を落とさずに10年間、株を持たせることです。「仕立て」次第で株の持ちが変わってきます。バラの栽培は温室内の環境管理がとても重要ですが、ベストな環境が周辺の気象条件で常に変化するため、思い通りにいかないことのほうが多いそうです。
新たな技術も チャレンジできる雰囲気に
剛世さんはバラの収穫後すぐに切り口を水に浸けるようにしています。また、切った花は肩に抱えず、採花車と呼ばれる車で運ぶようにしています。花弁を傷つけず、効率的に多くの花を運ぶためです。作業の一つひとつを徹底することが品質の維持・向上につながっています。部会では、高温対策として遮熱材の導入や、病気の対策としてUVB(紫外線)ランプの導入など、新たな技術を試験的に取り組んでいます。また、農薬を植物由来の資材に代用するなど環境への取り組みも試験的に行っています。「新たな考え方や取り組みを否定するのではなくチャレンジできるようにしたい」と剛世さんは話します。
そんな剛世さんは就農してから、「バラを花瓶に飾っておくと毎日雰囲気が変わっていくのだと知って感動した。ぜひ、花が最大限開くその瞬間まで楽しんでもらいたい」と話してくれました。

部会とともに
花き課 バラ部会担当
神谷 俊成さん
お互いの印象は?
遠山さん:真面目な人という印象です。
神谷さん:端的に言うように工夫してくださり、語彙が豊富な人という印象です。
あなたにとってどんな存在ですか?
遠山さん:指導員として私が期待することをしっかりとやってくれます。困った時に知識を提供してくれる存在です。
神谷さん:部会の中でも意見を言ってくれて、周りの人の笑顔も作ってくれるムードメーカーのような存在だと思います。
相手の方にメッセージをどうぞ
遠山さん:このまま頑張ってほしいと思います。が、いつも忙しそうなので少し気を使います。でも、どんどん聞きます!
神谷さん:いっしょに頑張っていきましょう!

遠山さんが所属している
バラ部会
| 生産者数 | 33名 |
| 販売数量 | 1,500万本 |
| 栽培面積 | 17ha |
| 販売金額 | 12.6億円 |
「高品質のバラを消費者に…」を合言葉に、収穫・出荷において厳しい基準を設けています。バラ部会は日本一の出荷量を誇ります。



一年中、一生続けられる趣味
大輪の菊に思いを込めて
大輪の菊に思いを込めて
白井 武雄さん
豊川市老人クラブ連合会 園芸部

約20年前、友人から苗をもらったことがきっかけで、武雄さんの菊作りが始まりました。何か没頭できる趣味がほしいと思っていた武雄さんはそれから毎年、菊作りに挑んでいます。 菊の仕立てにはいくつか種類があり、最も基本的なものが三本仕立てです。盆養(ぼんよう)とも呼ばれ、1本の苗から3本の枝を伸ばし、3つの花を咲かせます。初めに伸ばした枝が最も高くなることから、「天(てん)」と呼ばれ、2本目を「地(ち)」、3本目を「人(じん)」と呼びます。3つの花の高さ、大きさ、茎と葉の全体の調和が保つように育てます。仕立ての菊は根を張り巡らせることが大切です。最初の挿し芽から約20日で4号鉢に植え替え、また14日ほどで5、6号鉢、最後に9号鉢に植え替えます。武雄さんは、いつ植え替えをして、どのくらい肥料を与えたか、水はいつあげたかをカレンダーにびっしりと書き込んでいます。夏になると夕方5時から翌朝8時までをシェードで囲み、日照時間を調節します。花を咲かせる時期を調整するためです。
武雄さんは毎年、田原市の品評会に出品しています。今はドーム作りと呼ばれる仕立てで出品していますが、過去には三本仕立てで出品し、県知事賞を受賞しました。「最高位を受賞することが夢」と情熱を燃やします。
そんな武雄さんは「仲間がいてくれたから続けてこれた。園芸部では新たな仲間を募集しています」と笑顔で話してくれました。