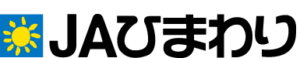管内のニュース
【グリーンセンター】スイートコーンの甘さを楽しんで

 グリーンセンター豊川・一宮・音羽では6月中旬に「とうもろこし祭り」を開催し、それに合わせグリーンセンターオリジナル商品「とうき美人」が販売されました。
グリーンセンター豊川・一宮・音羽では6月中旬に「とうもろこし祭り」を開催し、それに合わせグリーンセンターオリジナル商品「とうき美人」が販売されました。
「とうもろこし祭り」はスイートコーンをPRするイベントです。同イベントでは産直会員のスイートコーンの他、栽培技術の高い生産者が作る「とうき美人」も限定販売され、多くの来店者は採れたてのスイートコーンを買い求めていました。
「とうき美人」を栽培する酒井美代子さんは「スイートコーンは収穫から時間が経つと食味が落ちてしまうので、グリーンセンターや産直ひろばで地元産の採れたてで鮮度の良い美味しいスイートコーンを食べてほしい」と笑顔で話しました。
【JAひまわりスマート農業研究会】大学などと連携して生産量増加を目指す



JAひまわりスマート農業研究会は、昨年度より国の「スマート農業実証プロジェクト」に参加し、県や豊橋技術科学大学などの10機関と協力しながら、収量の増加を目指しています。
近年、先進的農業技術で、植物に快適な栽培環境をつくり、収穫量を増やす取り組みが進んでいます。今回、大学などと連携し、専用装置を使い、生育条件を変えて最適な栽培環境を模索しています。
【JAひまわりつまもの部会と東三温室園芸農協の大葉部会が協調】両団体がオオバの包装を一新


つまもの部会と東三温室園芸農協は初の試みとして、オオバの包装に「とよかわブランド」のロゴと「愛知県産」を印字し、共通ブランドとしてPRしていきます。
オオバは、コロナ禍で飲食店が営業自粛した影響で業務用を中心に昨年に比べ販売額が大きく落ち込んだ一方、〝巣ごもり需要〟で小売り向け小袋の出荷数が伸びています。そこで、両団体は「とよかわ大葉」としてPRすることで販売促進の起爆剤にしたいと考えています。
両団体が生産するオオバは、栽培面積が約30haで販売高が約50億円と全国トップクラスを誇ります。昨年2月に、豊川市観光協会から「とよかわ大葉」の名称でブランド認定されました。
【小坂井支店×母の日】女性来店者にカーネーション手渡す



小坂井支店は母の日にちなみ、5月7日、管内で生産されたカーネーションを50名の女性来客者にプレゼントしました。
同支店では、毎年支店活動の一環として母の日にカーネーション、父の日にバラをプレゼントしています。
花を受け取った来店者は「花をもらえると思ってなかったので驚いた。きれいな花はもらうとうれしい気持ちになるし、心が癒される」と笑顔で話しました。
【JAひまわり独自の緊急支援】コロナ禍の影響による農産物価格下落に対する支援



当JAは令和2年度に新型コロナウイルスの影響で収入が減った農家に対してJA独自の緊急支援を行い、支援総額は約2,000万円に上りました。
昨年4月からの新型コロナウイルスの感染拡大に伴う全国を対象とした緊急事態宣言の発出による経済活動の大幅な減退により、当JAの農畜産物は大きな影響を受けています。一部の農家では農業経営の悪化も顕在化しています。このような状況を踏まえ、価格下落が大きな品目を生産する当JAの生産組織と、管内の東三温室園芸農協に所属する組合員を対象とした緊急的な支援策を講じました。なお、価格安定事業などの公的にセーフティーネットが整備されている品目は対象から除きました。
支援内容は販売単価が過去3カ年の平均販売単価と比較し20%以上下落した品目を出荷した農家を対象に、当JAの購買事業と販売事業の利用額に対して、一定の割合を乗じた金額を支援しました。支援総額は購買事業で約1,300万円、販売事業で約700万円でした。 なお、令和3年度も緊急支援を実施します。
【「とよかわトマト」「とよかわミニトマト」がブランド認定】地元の方にもっと食べてほしい


とまと部会とミニトマト部会は5月31日に豊川市観光協会が主催するとよかわブランド認定証贈呈式で認定証を授与されました。
今回認定されたとまと部会が作る「とよかわトマト」は42ヘクタールの作付面積で出荷量が多く、販売金額は年間約10億円に上ります。また、食味と色艶の良さから市場での評価が高く、高糖度の「ロッソトマト」や「匠トマト」などのこだわりのトマトも高く評価されました。ミニトマト部会の作る「とよかわミニトマト」は全国に先駆けてミニトマトの栽培を始め、甘みと酸味のバランスが良く、赤色が濃いことから「ハニーレット」という名称で商標登録されています。作付面積は約12ヘクタールで年間の販売金額は約9億円に上ります。こうしたブランド化の取り組みや出荷量や品質の高さが評価されました。
とまと部会の天野恒雄部会長は「コロナ禍でトマトの価格が低迷している中、今回の認定を受けて、地元での販売PRにつなげたい。これからも安全・安心なトマトを作っていきたい」と話しました。